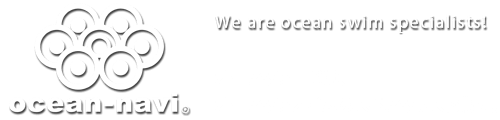オーシャンナビの会員さんに直撃インタビューするLet’s Talk。第5回目はスペシャルゲスト、新代田でも時々練習されているパラリンピアンの石浦智美さんにご登場いただきます。《前編》の今回は東京2020出場までの道のりと、その舞台に立って感じたことについてうかがいました。
|
File 05【アスリート編 前編】石浦智美さん
|
|
1988年生まれ、新潟県出身。先天性の緑内障による視覚障害を持つ。東京大会でパラリンピック初出場を果たし、S11という全盲クラスで、個人2種目と、混合リレーに出場。50m自由型で7位入賞、100m自由型でも8位入賞、そして混合400mリレーでは5位入賞。
|
自国開催で集まったパラスポーツへの注目が
理解や共感につながって欲しいと思います。
――まずは水泳を始めたきっかけから教えてください。
喘息気味で病弱だったので、ドクターからすすめられて2歳からプールに入っていました。兄が水泳をやっていたこともあって水への恐怖もなく、自然と遊びの感覚で始めたんです。私は生まれつき視覚障害があるんですが、子供の頃はまだ文字も見えていましたし、杖も持たず一人で歩けていたので、一般の子と一緒にレッスンもできたし、泳ぎやターンも見て覚えることができていました。
――競技として取り組み始めたのはいつ頃からですか?
小学校4年生の時、障害者水泳の指導をされている方と出会ったのがきっかけです。小学校では健常者と同じ水泳大会に出ていて、同じ障害を持つ人との交流もなかったし、そういう大会の存在もよく知らなかったんです。同じ頃に長野オリンピックもありましたが、パラリンピックのことはあまり報道されなかった時代です。まだ障害を持った人が社会に出たり、ましてやスポーツをやるという時代ではなかったので、人数も少なく、大会で泳げばメダルをとれたという感じでした。
中学までは地元の新潟にいたんですが、高校から東京の筑波大学附属視覚特別支援学校で本格的に競技に取り組むようになりました。同世代の仲間と切磋琢磨して競技力を磨いていった時代です。
――パラリンピックが具体的な目標となったのはいつ頃からですか?
パラ水泳では2000年ごろから成田真由美さんが活躍されましたし、全盲スイマーの河合純一さんも世界で活躍されていたので、それを見て、将来は自分もそういう舞台に立ちたいという思いが芽生えました。高校時代には同級生がアテネ大会に出場してそれも刺激になりました。そんななかで、北京、ロンドン、リオを目指そうという気持ちになっていったのですが、なかなか目標に近づくことができなくて・・・。
――パラリンピックの代表選考は、どのような基準があるんですか? オリンピックの水泳とはまた違うのでしょうか?
オリンピックの場合、各種目で派遣タイムを切ったうえで1位と2位の選手が代表になるんですけど、パラリンピックは国内の個人の戦いの前に、日本全体としての枠取りがあるんです。なので、国内だけじゃなくて常に世界のレベルをチェックしなくてはならない。さらにリオからはメダル獲得を照準にした派遣タイムというものも設定されて、リオの時はそれに0.3秒足りず補欠になってしまったんです。その時思ったのが、出場ではなくメダルがとれる水準の記録を目指していかなければ、代表にはなれないんだということでした。
――厳しい世界ですね。東京を目指すにあたっては、転職までして環境を変えたそうですね。
はい。以前は大学を卒業して採用された企業でフルタイムで仕事をしていました。視覚障害があるので、仕事をみつけるのは健常者よりも厳しい面があるんです。それもあって、まずは社会人としてやっていくことを優先して、競技はプライベートの範囲内で続けるという方針でやってきました。練習は勤務が終わってからの時間帯で、国際大会の参加もすべて有給休暇を使う形で、経済的な支援も受けることなくロンドン、リオを目指してきたんですが、資金的にはコーチやタッパー(視覚障害の選手にターンやゴールのタイミングを知らせる補助員)をお願いするのも難しい状況でした。
ただ、世界のレベルがどんどん上がっている中で、それではメダルどころかパラリンピックに出ることさえ難しいと感じたんです。ほかの国では、支援を得てパラに出ることが仕事のようになっている選手や、メダルをとれば一生暮らしていける、というような環境にいる選手も多い。そういう選手たちを相手に勝負して、金メダルをとるという目標に到達するには、今のままでは難しいのかなと。それで、当時のコーチにもすすめられて、アスリート就職支援制度を利用し、練習時間を確保できる環境を手に入れたんです。正社員から契約社員になってしまうのはかなりの不安があり最後まで迷いましたけど、やっぱりここまでやってきたからには東京で代表入りをしたいという思いがあって決断しました。
――人生を賭けた決断ですよね。出場が決まって、どんな思いでしたか?
うれしさよりも、ホッとしたのが一番ですね。正直な話、2020年に選考会が開催されていたら、厳しかったんです。基準タイムに自分のベストタイムが0.03秒足りていない状態でしたし、直前にオーバーワークによる故障もあったので。延期になったことで故障を治す時間もできたし、ベストタイムも更新できて心にゆとりもできて。とにかくクリアできてよかったっていう気持ちでした。
――初めてのパラリンピックの舞台、どういう体験になりましたか?
自国開催だし、無観客だしということで、始まるまではパラリンピックも他の国際大会もそんなに変わらないんじゃないかと思っていたんです。街や会場の装飾のような視覚的な情報も入ってこないですし。だけどいざ出場してみたら、やっぱり違ってましたね。選手たちがこの大会にかけてくる熱量が違う。コロナ禍で大会数が少なかったので、ほかの選手の状態がつかみにくくて、トップのタイムにしても、想定していたものと実際のタイムに大きな乖離がありました。
技術面や体力面が万全だとしても、メンタル的な要素とか雰囲気とか、そういうものがからんでくるのがパラなんだと思いました。みんな余裕がなくなってしまう環境で、いかに自分を失わずに競技に集中できるか。いろんな要素が絡み合うなかで、すべてが揃った状態の人が金メダルをとれるのだなと、そういう印象を持ちました。
――終わってみて、周囲の反応などはどうでしたか?
今回、無観客という形での開催でしたが、その分みんなテレビで注目して見てくれていて、最近連絡をとっていなかった大学の友達が連絡をくれたり、地元の小学校や幼稚園の子供達が応援してくれたりと、多くの人からうれしい反応がありました。自国開催によってパラスポーツが身近な存在になったように思います。テレビなどで放送される時間も過去になく多かったですから。そういう意味で、無観客もよかったのかも知れません。
――改めて、パラリンピックの意義をどう感じていますか?
私としては、パラスポーツで戦う選手の姿を見ていただくことで、障害への理解や共生社会につながっていけば、という思いがあります。最近は競技としての面白さを感じて見る方も増えていて、それもうれしいです。活躍する選手を見て、「この選手は普段の生活でどう障害を克服しているんだろう」とか、「うちで社員として活躍してもらえないだろうか」とか、そういう発想につながってくれたらいいなと思いますね。
パラアスリートはいろんな葛藤を乗り越えてこの舞台に立ってる人が多いんです。スポーツだけじゃなく社会人として活躍できるポテンシャルがあると思うので、今後そういう視点を持っていただけるきっかけになるといいなと思います。
※《後編》では、視覚障害を持って泳ぐということについて、お話しいただきます。
|
取材日:2021年9月 取材・文:東海林美佳 ライター。一般誌、企業誌、スポーツ専門メディアなどに寄稿。東京2020でパラスポーツの面白さに開眼していたまさにその時、久々に新代田に来ていた石浦さんにお会いして、厚かましくもその場で取材を申し込んでしまいました。石浦さん、快く取材を引き受けていただき、ありがとうございました! |
 |